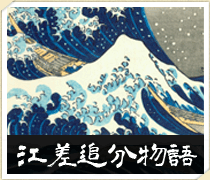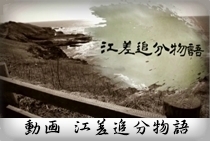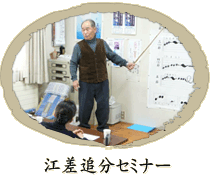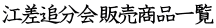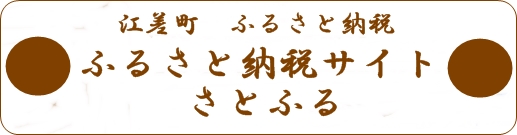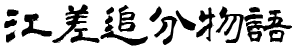忍路高島
伝説の大方は、元禄初期以来と伝えられる神威岬の女人通行禁制を、つよく意識して作られたものである。
ともあれ、この禁制は、不幸にして迷信深い水主(かこ)達によって幕末の頃まで堅く守られ、後世、幾多の愛別離苦の悲劇を生むもとになった。
「忍路高島」が、その間の事情を端的に物語る歌詞であることは、いうまでもない。
では、なぜこれほど長い間、和人が奥場所へ定住することをさまたげる、このような禁制が行われたのであろうか。
その原因を尋ねてみると、そこには松前地の繁栄のみを守ろうとし、奥地における支配の内情が外部にもれることを恐れた松前藩のこそくな政策があった。
そのような施政の下におかれ、過酷な労働を余儀なくされた人々こそ災難であったといわなければならない。
つまり、大勢の出稼ぎ漁夫やその家族、小前の百姓達、旅芸人や花街の女といったような下積みの人々である。江差追分は、何よりも、まず、そのような人々の胸奥からほとばしり出た魂の叫びであった。
それにしても、一つの人を感動させるに足るものが、世に生まれ出てくるためには、何と大きな犠牲を払わなければならないものか、それら無数の先祖の気持ちを思うにつけ暗然とした気持ちにならざるを得ない。
「忍路高島」が唄われ始めた時期については、きわめておぼろげながら推定する手掛かりが全くないわけではない。
つまり、この文句の原型をたどって行くと、天明年間に幕閣で権勢をふるった老中の田沼意次にちなんだ
「田沼様には及びもないが、せめてなりたや公方様」
という当時の江戸での流行り唄に行きつくからである。
この唄はまもなく地方に移って、越後の新発田あたりでは「新発田五万石およびもないが、せめてなりたやとのさまに」(松坂節)、酒田では「本間様にはおよびもないが、せめてなりたやとのさまに」(酒田節)という風に替え唄として唄われた。
とすれば当然、その延長上に、わが北海道の「忍路高島」も位置すると考えてよいわけである。
ところで、唄が流行するまでの経緯はどうであれ、単なる羨望の気持ちを表した上記のような唄は、人の心をうつという点で「忍路高島」のもつ迫力には、遠く及ばないのではないだろうか。
所詮、民謡というものは、その時々の人の心の在り所によって、いかようにもその価値、内容が変わり得るものである。
この点に関し、風俗画報所載の関係記事の筆者である山下重民氏は、同誌の中で、
「およそ俚謡の人を感動せしむるはその真率なるにあり。そのことの実際より出るに因るなり。この追分の一曲、以って証すべし」
と述べられておられるが、まことに至言といえよう。
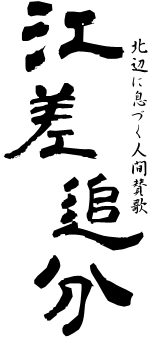
 正調江差追分「ロゴマーク」使用申請はこちらをクリック
正調江差追分「ロゴマーク」使用申請はこちらをクリック