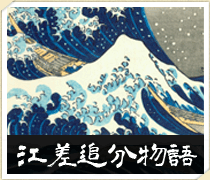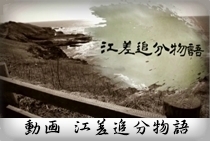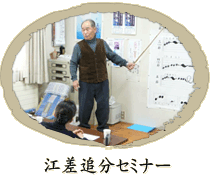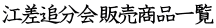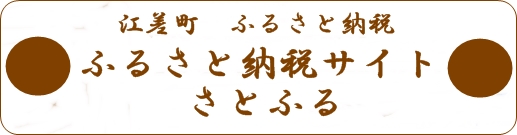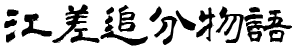佐之市と芸者亀吉
いまは曲節が失われた地元の古い民謡「天保問屋荷揚唄」の中に「追分はじめは佐之市坊主で、芸者のはじめは蔦屋のかめこ」とある。 寛政の頃、南部の盛岡辺から流れてきたとされているこの旅芸人は、江差の切石町の妓楼に姿を現す...続きを読む
義経伝説
文治5年の秋、奥州を逃れた義経主従は、一葉の軽舟に身を托して、はるばる蝦夷地に渡ってきた。積丹半島の辺りに上陸した義経は、まず長老のシタカベを従え、しばらく彼の地に滞在した。 やがて、シタカベの娘のフミキ姫は、許婚...続きを読む
平野源三郎
平野師は明治2年10月、木古内町下町の生まれ、14歳のとき、親戚筋に当たる江差の平野屋の養子となり、鴎島学校を優秀な成績で卒業したあと、家業の呉服行商に従事した。 平野師と追分節を最初に結びつけたのは、養母のリカ女...続きを読む
二声上げ、七ッ節
明治42年末の師匠会議以降、地元の追分界で唄い方の基本とされるようになった言葉に「二声(ふたこえ)上げ、七ッ節」というのがある。 これらは人によっては「七節七声、二子上げ」とも表現するが、いずれの場合も江差追分の本...続きを読む
追分節演奏大会
明治末期から大正の中期におよぶ、第一次の追分ブームをまき起こすきっかけをつくったのは、明治45年の6月から7月にかけて平野源三郎師が参加して行われた追分節演奏大会であった。 前年の秋、地元の追分大会に優勝した師は、...続きを読む
前唄・後唄
前唄が完成するまでには下海岸石崎の網元として知られた川島仙蔵師の功績が大きく、後唄の導入に当たっては関西尺八界の泰斗内田秀童師が大きな役割を果たしたといわれる。 また、これら三部構成の演唱形式を一般的に普及した功労...続きを読む
忍路高島
伝説の大方は、元禄初期以来と伝えられる神威岬の女人通行禁制を、つよく意識して作られたものである。 ともあれ、この禁制は、不幸にして迷信深い水主(かこ)達によって幕末の頃まで堅く守られ、後...続きを読む
追分会館演示室「緞帳」と初代浜田喜一師
「地元では追分を唄わないという師の返事は、少なからず私を驚かせた。 しかし、引き続いてお話しを伺っているうちに、その真意は決して江差をきらってのことではなく、中央の芸能人と地方の民謡伝承者という、立場の相違から来る...続きを読む
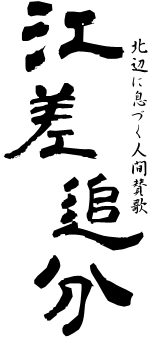
 正調江差追分「ロゴマーク」使用申請はこちらをクリック
正調江差追分「ロゴマーク」使用申請はこちらをクリック