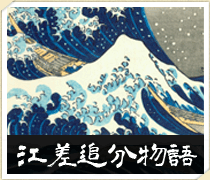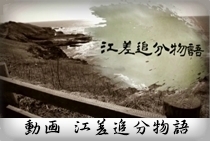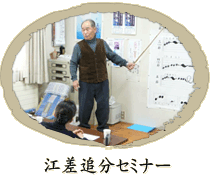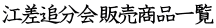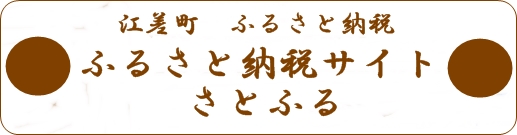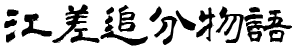佐之市と芸者亀吉
いまは曲節が失われた地元の古い民謡「天保問屋荷揚唄」の中に「追分はじめは佐之市坊主で、芸者のはじめは蔦屋のかめこ」とある。
寛政の頃、南部の盛岡辺から流れてきたとされているこの旅芸人は、江差の切石町の妓楼に姿を現すや持前の美声と当意即妙の歌詞、座持ちのよさなどで酒席を賑わし、たちまちのうちに土地の人気者になってしまった。佐之市が得意とした歌は、けんりょう節、じょんがら節、あいや節などたくさんあったようであるが、何といっても出色なのは追分節であった。
彼はこの歌を「松前」や、三下りなどという既存の過渡的な曲調の唄を基本に、けんりょう節の長所をとりいれて、今日につながる江差追分の原型をつくり上げて行ったようである。
数ある追分節の文句のうち、佐之市が最も得意としたのは
色の道にも追分あらば、こんな迷いはせまいもの
という一句で、彼はこの文句を、当時、切石町の妓楼で客の種を宿して苦しんでいたある女の身の上に同情して創作したという。
蔦屋のかめ女については、その没年が慶応2年7月28日(ただし享年不詳)であることがわかっている。彼女は江差の古い料亭蔦屋の娘で、芸名を亀吉といい、生前、常磐津など各種の音曲を能くした人であったらしい。唄本の裏表紙とみられる署名入りの紙片が一枚、今日に遺されている。追分は佐之市がこの人に伝授して唄わせたとも伝えられるが、もしそうであるとすれば、晩年、花柳界の大御所的な存在になっていた佐之市が、弘化、嘉永、安政と続く幕末のいずれかの時期に、後輩である彼女に唄わせ、折々の座興に供したものであろう。
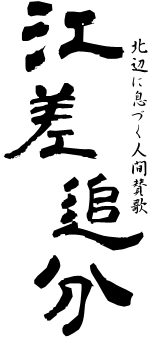
 正調江差追分「ロゴマーク」使用申請はこちらをクリック
正調江差追分「ロゴマーク」使用申請はこちらをクリック