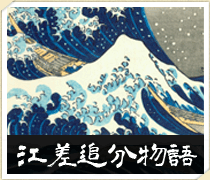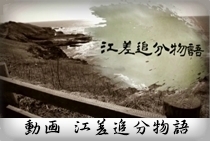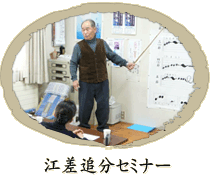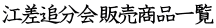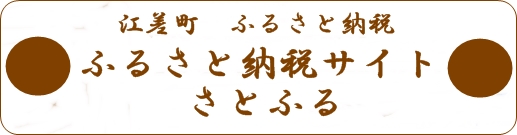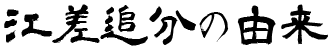一.江差追分の起源
江差追分の起源は明治30年以降、川竹駒吉・森野小桃・村田弥六・岡田健蔵・高橋掬太郎・三木如蜂・阿部たつを・白石武臣等の追分研究者がその著書で述べているが、定説として決定的にできるものはない。
特に、発生年代となると江戸時代中期以降とするだけで、確定的なものは出ていない。 民謡や民俗芸能は本来長い年月のなかで郷土に溶けこみ定型化するもので、自然発生的要素が多いものであり、江差追分も古い時代に江差の風土と結合し郷土の先人が育て、唄い伝えてきたもので、その発生過程を明らかにできないのは、むしろ民謡としての本質によるものであろう。
特に渡海者の移住によって発生した北海道の郷土文化は、本州各地から運ばれたものが複合され環境に根付いた生活慣習も、その中から生まれたものであり、江差追分もその例にもれるものではない。
言い伝えや研究者の著述の中で、江差追分の起源を信州小諸付近の追分節が、越後に伝わり、越後追分となって船で蝦夷地に渡り、一方それより先、越後から松坂くずしが伝わり、謙良節として唄われていたものとが結合して江差追分になったとする説がほとんど定説となっている。
即ち信州北佐久郡長倉村追分付近の街道を上下する馬子たちによって唄われていた馬子唄(馬方節・信濃追分)が参勤交代の北陸武士や旅人瞽女(ごぜ)等によって越後に伝わり蹄の音が波の音、即ち山野のメロディーが海辺のメロディーに変化して越後追分(古くは松前、または松前節と呼ばれた)となり、船乗りに唄われ北前船によって蝦夷地に伝わり謙良節と合流し、蝦夷地という辺境の荒い波濤の中で哀調を加え、江差追分が生まれたという。
この過程で追分の原型に近く哀愁をおびて唄い伝えられたのが「江差三下り」であり、謙良節と合流し地味で悲哀の感情をこめ「二上り」の調子に変わって唄い継がれたのが江差追分である。
何れにせよ信州地方の追分節を母体に、その原型を堅持したのが「江差三下り」であり、調子を二上りに変え、比類なく曲節を練り上げたものが「江差追分」である。
さて、江差追分の源流を信濃追分に求めるのは定説であるが、この信濃追分の発生についても異説が多い。
岡田健蔵氏は、伊勢伊賀の馬子唄が東海道から中仙道を経て木曽路に入り、木曽馬方節となり信州小諸に伝わって追分節になったとし、柳田国男氏は信州追分のメロディーにイタコの神おろし唄と共通なものがあるとして古い時代の追分調メロディーの普遍性を指摘している。
また、近年メロディーの近似性から蒙古民謡に源流を求め、貢馬とともに信州に入り、馬子の唄として成立したという説もある。
発生の古いものほど異説も多く、このことは民謡のもつ本質のひとつであろうと思われる。 一方いまひとつ江差追分の父といわれる古い型の謙良節は、現在では唄う人もなく消えうせているが、伊勢松坂の民謡「松坂節」が越後に入って祝唄の越後松坂となり、のちに「松坂くずし」として唄われていたものらしい。
天明(1781~1788年)の頃、越後新発田(または新津出身ともいう)の松崎謙良(座頭)が松前に渡り、松前家の重臣下国季寿のもとに寄寓し越後松坂くずしを巧みに唄っていたので謙艮節と呼ばれるようになったという。
また、寛政の頃(一説には天保年間)に南部盛岡の琵琶師の座頭佐之屋市之丞こと佐之市(一節に長崎生まれ、船頭の息子)が江差に渡り、酒席をとりもち美声で唄う謙良節が評判になったという。
「あやこ(酌婦)よければ 座敷がもめる、もめる座敷は謙良節」という歌詞が残っている。
こうして江差で唄われていた謙良節をもとに、越後追分を加えて編曲し、作詞して「二上り」の調子で唄いひろめたのが佐之市であると伝えられている。
「追分はじめは佐之市坊主で 芸者のはじめは蔦屋のかめ子」と唄われ佐之市の作詞とされるものに「恋の道にも追分あらば こんな迷いはせまいもの」という追分の歌詞が伝えられている。
もちろん楽譜もない時代で佐之市の唄がどんなものであったか知るすべもないが、江差追分成立の過程として無視することはできないであろう。
江差追分は謙良節を父とし、越後追分を母として海浜に生きる江差地方の風土に溶け込み、特色ある生活環境や、労働形態の中で幾多の変遷を経ながら育まれたものである。
以上定説とされるもののほか、アイヌ唄から発生したという異説もある。
即ち、村田弥六師が説くその唄というのはメノコが丸木舟に乗って車櫂を操りながら、波の間に間に悲しい調べで唄うもので、和人がこれを聞きアイヌ語を翻訳して唄ったのが追分節であるというものであるが、高橋掬太郎氏等はこれを否定している。 また、義経伝説にからむアイヌ首長の娘「チャレンカ(或いはフミキ)」との悲話から片恋に死んだ哀れなメノコの霊を弔う悲しい調べが江差追分を発生させたとする説を、森野小桃氏等が述べているが、この義経伝説にまつわる江差追分発祥説は明冶期の創作伝説と考えられる。
ともあれ江差追分の発生に、こうした異説が多くあるということは、この唄がそれだけ世人の好尚に叶い、関心を集めている証左であろう。
謙良節を父に、越後追分を母として、ふたつの唄の持つ要素が江差追分を生んだとしても、それは母胎であってその他各地から運ばれた種々の唄の特徴が加わり、時にはメノコの唄うアイヌの唄の調子等も加わったということも考えられる。
ともあれ江差は有カな漁場及び商港として蝦夷地という当時の辺境のなかで、江差追分を独特の情緒をもつ唄として完成したものであろう。
この江差追分の発生年代は、明和~寛政(1764~1800)年代にあたる松前13代藩主道広の頃とされている。
この時代は藩政の頽廃期にあたり、よくいえば優雅風流、悪くいえば浮華淫靡で有カな座敷唄が生まれる温床として好適な時代であり、江差追分は一面そのような背景のもとに育ったのであろう。
補足資料
- *1 追分はじめは佐之市坊主で 芸者のはじめは蔦屋のかめ子
…佐ノ市と芸者亀吉(出展:江差追分物語) - *2 義経伝説
…義経伝説(出展:江差追分物語)
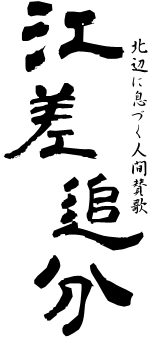
 正調江差追分「ロゴマーク」使用申請はこちらをクリック
正調江差追分「ロゴマーク」使用申請はこちらをクリック